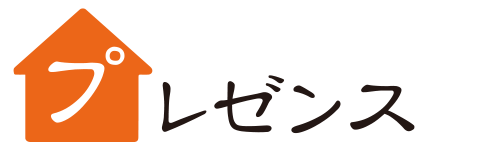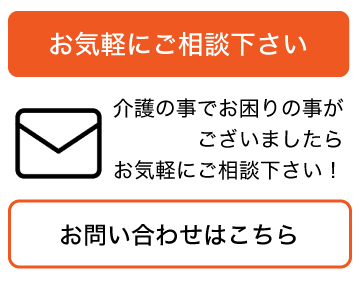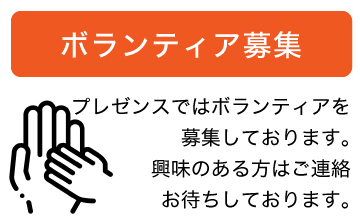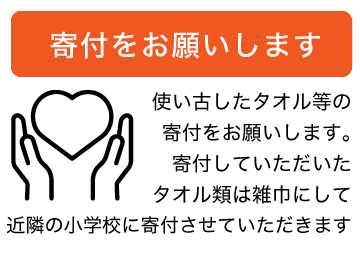アルコールチェックの義務化【介護施設・老人ホーム】
2022年4月と2022年10月からそれぞれ運転前のアルコールチェックが義務化される事となりました。義務化されること運送業など運ぶことを業務としている「緑ナンバー」で義務化されていたアルコール検知器でのチェックについて、あらたに自社製品の配送など「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者も対象になりました。改正の端緒となったのは、2021年6月に千葉県で白ナンバートラックによる飲酒運転事故が発生し、小学生5人が死傷する惨事となったことです。今回はアルコールチェック義務化について解説します。
目次
安全運転管理者の選任が必須
安全運転管理者の選任
アルコールチェック義務化にあたり、一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行なわなければなりません。
・定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
・その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
・自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
副安全運転管理者
・20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
・自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者、副安全運転管理者の選任は、次に掲げる要件を満たす方を選任する。
安全運転管理者
年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方
・運転管理実務経験2年以上
・公安委員会の認定を受けている
(専務・部長・課長等で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)
副安全運転管理者
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方
運転管理実務経験1年以上
運転経験3年以上
公安委員会の認定を受けている
(係長又は係長相当職以上で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)
上記の要件を満たしていても安全運転管理者に該当しないケース
・交通事故の場合の救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)
・酒酔い・酒気帯び運転又は、その下命容認行為
・妨害運転(いわゆるあおり運転)
・飲酒運転にかかわった車両・酒類の提供
・飲酒運転の車両への同乗
・過労運転(麻薬等運転を除く。)の下命容認行為
・放置駐車違反の下命容認行為
・積載制限違反の下命容認行為
・無免許運転違反の下命容認行為
・大型自動車等の無資格運転の下命容認行為
・最高速度違反の下命容認行為
・自動車の使用制限命令違反
安全運転管理者の業務
①運転者の状況把握
運転者の運転適性や、安全運転に関する技能・知識・道路交通法の遵守の状況を把握する
②運転者の適性等の把握
業務上で社用車を使用するドライバーについて、その者のドライバーとしての特性、運転技能、自動車に係る知識、安全運転に係る知識、その他に交通規則を遵守しているかどうかについて把握する
③安全運転確保のための運行計画作成
最高速度違反や、過積載・過労運転・駐車違反等の防止や、その他安全運転を確保するように留意し、自動車の運行計画を作成する
④交替運転者の配置
運転者が長距離・夜間の運転をするとき、疲労などにより安全運転の継続ができない恐れがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置する
⑤異常気象時の安全確保の措置
異常気象や、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障があるときは、運転者に対する指示や、安全運転を確保する措置を講じる
⑥点呼等による安全運転の指示
自動車の運行前点検や、飲酒・過労・病気その他の理由により正常な運転ができるかどうかを把握し、安全運転を確保するために必要な指示を与える
⑦運転日誌の備付け
運転者名、運転開始・終了日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させる
⑧安全運転指導
交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの教育を行う
安全運転管理者の届出
・安全運転管理者を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要な書類を提出する。
2022年4月1日以降に義務化
・酒気帯びの有無を確認。
運転前後の運転者の状態を目視等で確認して、運転者の酒気帯びの有無を確認することとなります。
・酒気帯びの有無記録を保存する
酒気帯びの有無の確認内容を記録し、その記録を1年間保存。
・検知器は使用をした検査の実施はなし。
※運転前後とは運転中にも飲んでないかを確認することとなります。
2022年10月1日以降に義務化
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、アルコール検知器※1を用いて、酒気帯びの有無を確認。
・アルコール検知器を、常時有効に保持する。
※1 呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音・警告灯・数値等により示す機能を有する機器
参考資料
警察庁のリンクページとなります。
まとめ
今回は、企業がアルコールチェックの義務化の改正ついて解説してきました。アルコールチェックの義務化は、段階を踏んで法改正されます。記録保存のための準備やアルコール検知器の配備など企業が準備が必要です。対象の企業は、義務化開始に合わせ対応できるようできるよう対策してください。
介護施設(老人ホームやデイサービス)も高齢者を乗車させ移動する事が多い業種です。
介護施設(老人ホームやデイサービス)での送迎車などの台数を明確に把握し必要に応じた準備を行ってください。
プレゼンス介護施設相談室
介護についてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
日々の介護で困っている。
介護施設(有料老人ホーム等)の入居を検討している。
様々な悩みに出来る限り寄り添わせていただきます。
【住所】 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目22-11
(デイサービスプレゼンス事業所内)
【営業時間】10:00~17:30
【お問い合わせ】 お問い合わせはこちら